Contents
方言周圏論と地方の文化
言語学に、「方言周圏論」という仮説がある。
これは、文化や言葉(語や音)は中央から地方にかけて波及するという言説である。
先日、この方言周圏論を肌で体験した出来事があった。
地方の小さな港町に行った時である。出棺時に「荒縄」という文化があって驚いた。
「荒縄」は縁側にかけていた縄を出棺時に切って、屋根へ投げるという文化だった。
他にも「お清めの水」と言って、葬儀から帰ってきた親族たちの穢れを落とすために、水で手を洗い、穢れを落とすという文化も残っていた。
もちろん、荒縄もお清めの水も、現在都会では行われない文化である。
令和の時代において、まるで昭和かのような文化が残っていることに非常に驚かされた。
ちなみに語や音は方言周圏論というダイナミズムで変化するが、文法(grammar)は地方から中央に波及する逆方言周圏論で変化すると言われている。
ここら辺の言葉の移り変わりのダイナミズムは、スケールが大きくて面白い。
惣と町内
地方に残っている昔の文化に「町内」というものがある。
これは同じ地区の人同士が、清掃活動や街頭の電気代を支払ったり、祭りの手伝いや葬儀の時に張場を行ったりするための集まりである。
町内の人たちはひとつの共同体であるから、行事ごとに参加しないと、家の評判が悪くなる。
ま、一種の村八分ですな。
都会でもマンションに住んでいるとマンション管理組合などの共同体があると思うが、地方の町内は先祖からの付き合いなので、どちらが繋がりが深いかは言うまでもない。
地方で「町内」を見るたびに、私は中世室町時代の「惣」を想起するのである。
惣とは、中世日本における百姓の自治的・地縁的結合による共同組織(村落形態)を指す言葉である。
この惣という共同体で、米づくりをしたり、徳政一揆を起こしていたりしたのですな。
およそ700年前の惣という文化が今も色濃く町内に残っているのだ。
私は地方の町内と接するたびに、シーラカンスと出会ったような感慨深い気持ちになる。
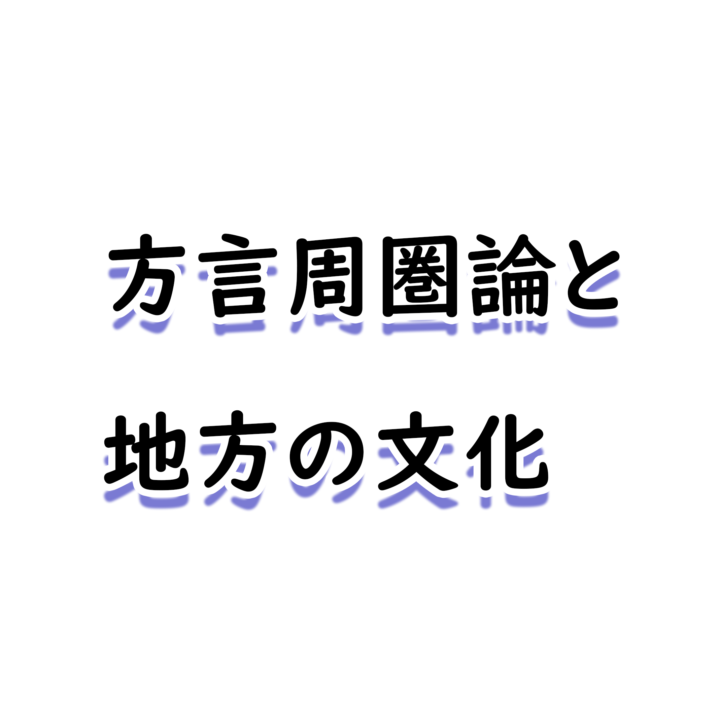
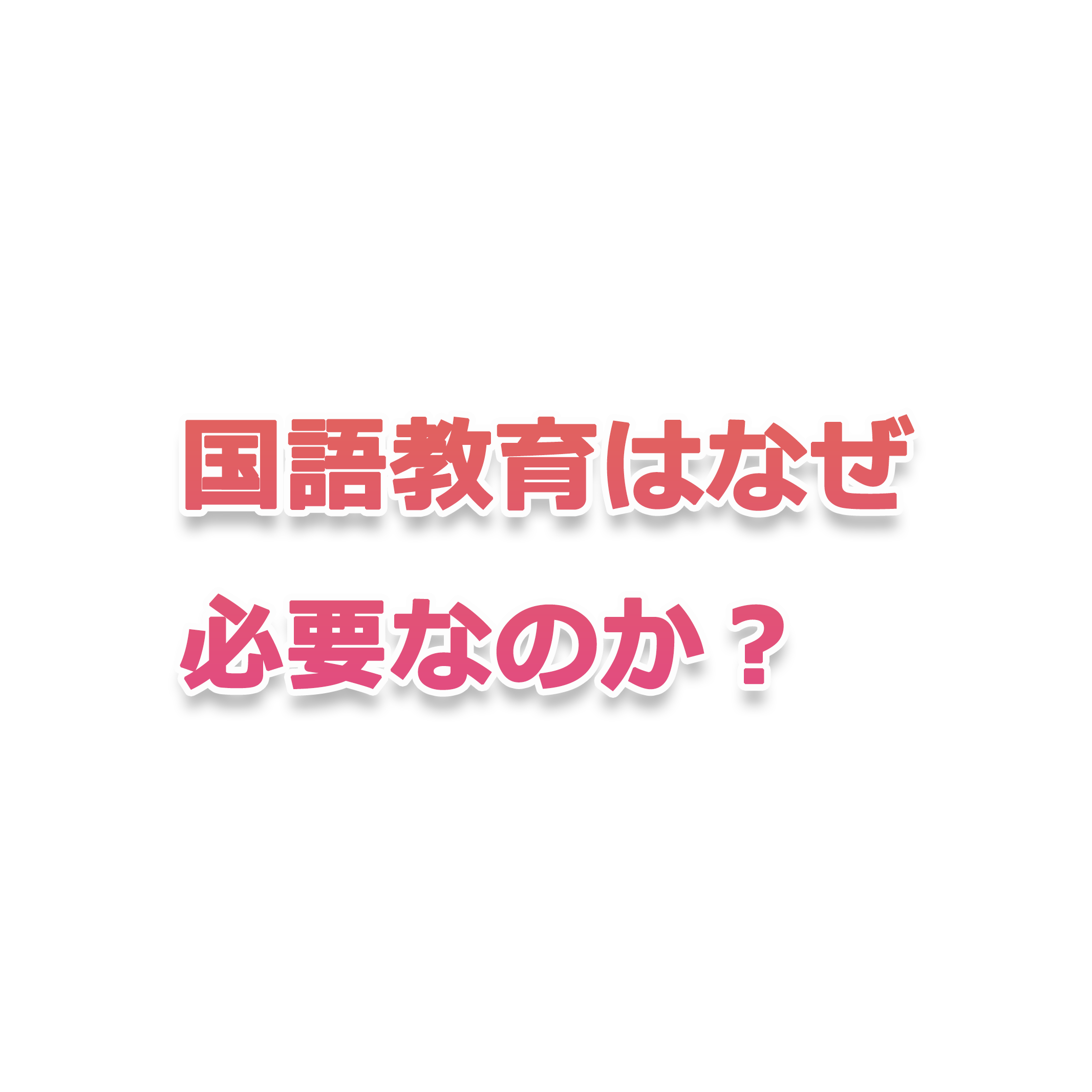
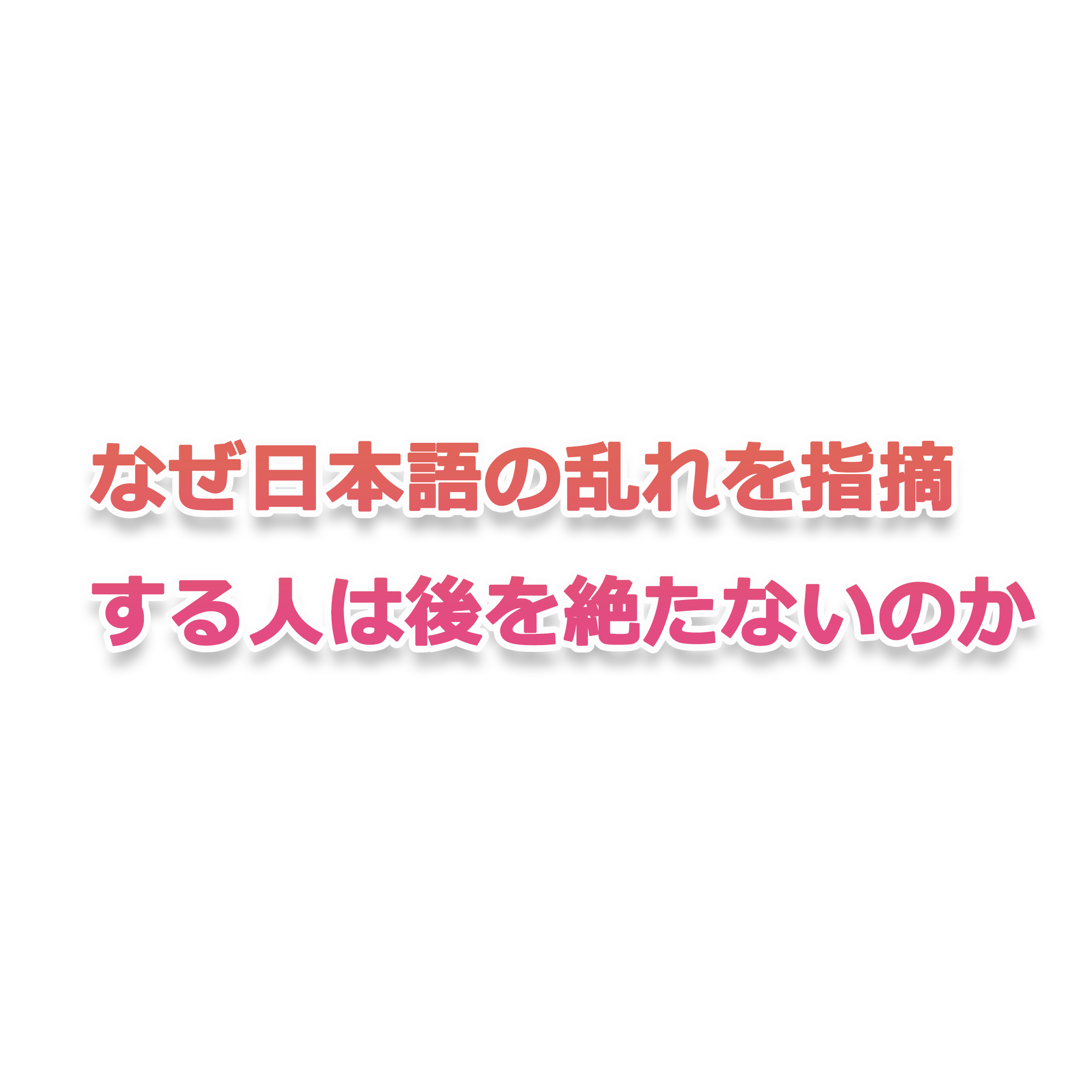
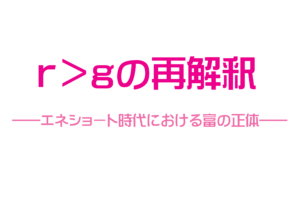
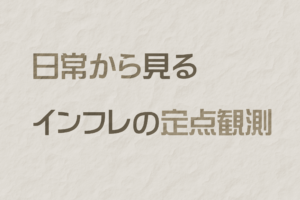
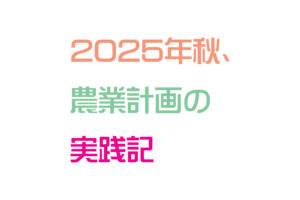

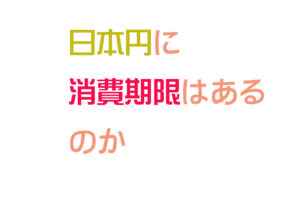

コメントを残す